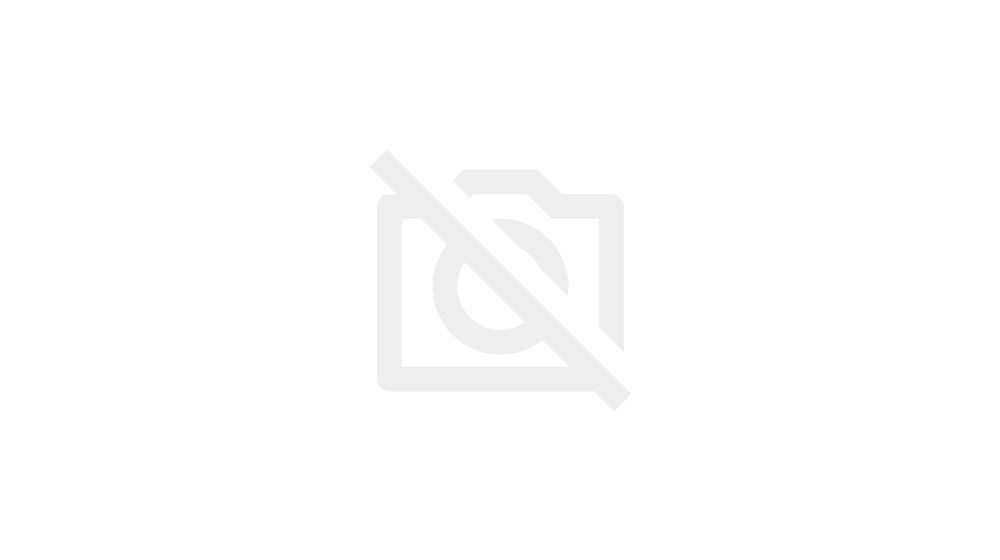司法書士 廣澤真太郎
この記事では、相続財産の調査のうち、とくに借金の調査にスポットを当てて解説していきたいと思います。

[toc]
相続人が亡くなった方の借金の有無を調査する方法

1.相続開始後、一段落したら相続財産の調査を開始しましょう
相続手続きを進めるため、まずは亡くなった方の相続財産を特定していく必要があります
この段階から司法書士に一部の財産調査をお任せいただく事も可能です。
具体的なプラス財産含む調査方法概略はこちらの記事に記載しています。
亡くなった親族と疎遠であり、どのような財産があるのか全く分からない場合
このような場合は急ぎでの対応が必要です
亡くなった親族の相続財産が全くわからない場合は、大急ぎで借金の有無を調査する必要があります。
例えば、プラスの財産よりも借金等の支払いのほうが多いといった、いわゆる債務超過の場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申立てを行う必要があるからです。
ケースにもよりますが、亡くなった方の部屋が荒れているときや、生活保護を受給されていたという事情が既に判明しているような場合には、
調査を省略し、速やかに家庭裁判所に相続放棄申述申立てを行うという事もあります。
注意点
法律では相続放棄の熟慮期間は、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」とされていますが、相続開始を知った日付を疎明する資料がないという事が実際にはよくあります。
このような場合は、「死亡日から3ヶ月以内」に申立てをしておくというのが最も無難です。
とくに親子間などは相続開始を知った日は当日なのではないかと推認するのが一般的な感覚であり、疎明資料がないのに説明さえできれば受理されるという事になれば、
実質いつでも相続放棄できることとなってしまい制度の趣旨に反してしまう事が考えられるからです。
2.多額の借金や支払いがあることが判明した場合
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしましょう
詳しくはこちらの記事(ランディングページ)の上部をご覧ください。
具体的には必要な戸籍類を収集し、管轄の家庭裁判所に申立書を提出後、その内容が認められれば受理されるという取り扱いとなります。
借金の調査が3ヶ月の期間に間に合わない場合
管轄の家庭裁判所に期間延長申立てをすることができます
借金がないのなら相続したいと考えているが、借金調査が間に合わないという場合、3ヶ月の期間を延長してもらって引き続き調査するという方法もあります。
調査の動き出しが期限ギリギリのときなどに利用することが考えられますね。
3.具体的な借金の調査方法

【KSC・JICC・CIC】に開示請求 及び 故人が残した資料を確認しましょう
大丈夫です。表にしましたので、次のように理解してください。
| 信用情報の保管機関の名称 |
|
| KSC |
銀行・信用金庫等に対する借入調査先 |
| JICC |
消費者金融に対する借入調査先 |
| CIC |
クレジットカードや消費者金融に対する借入調査先 |
「信用情報」は金融機関がお金を貸すかどうか審査する際に、その判断基準として利用する情報ですが、その信用情報を保管しているのが上記の3機関だとお考えいただければ結構です。
よって、この3つの機関に相続人から開示請求を行えば、金融機関などに対する借金の存在を確認する事ができるという事ですね。
ただし、これだけでは個人間の借金の存在や、契約上の保証人としての地位などが確認できるわけではありませんから、亡くなった方の手元にある通帳・契約書・請求書などの資料から、網羅的に債務の確認を行っていく必要があります。
4.具体的なKSC・JICC・CICへの開示請求のやり方
事前に資料をある程度、準備しておきましょう
まとめて次の資料を揃えてしまいましょう。
開示請求に必要とされる書類
✅ 死亡日記載の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
✅ 亡くなった方と請求者の親族関係がわかる戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
※一部の機関で、必要書類が変更になり、「法定相続情報一覧図」がなければ開示できないという扱いになりました。相続放棄手続きに借金の全体像の調査が間に合わないことが予想されます。
✅ 請求者の運転免許証の両面コピー 3部
✅ 請求者の健康保険証の両面コピー 3部 ※住所記入も必要です
✅ 小為替1000円(発行後6ヶ月以内) 3部 ※郵便局で平日午後4時まで販売。
✅ その他必要に応じて … 相続関係説明図(相続人が直系尊属又は兄弟の場合)・速達、本人限定受取郵便希望の場合の小為替・前順位者の相続放棄申述受理証明書
※戸籍収集・法定相続情報一覧図・相続関係説明図の作成、相続人や相続財産の調査は司法書士にまとめてお任せいただけます。
各機関に請求をかけていきます
基本的に上記書類を送付すれば完了です。
内容に問題がなければ、それぞれ約2週間後に回答書がご自宅に到達します。
戸籍や法定相続情報一覧図は複数部取っておかないと、コピーで足るところもありますが、同時に進められなくなる可能性があるため注意しましょう。
KSC
KSCの郵送請求はこちらから
JICC
JICCの郵送又はオンライン請求、請求書のダウンロードはこちらから
CIC
CICの郵送又はオンライン請求、請求書のダウンロードはこちらから
故人の自宅を調査しましょう
個人的な借金や契約上の地位などは、実際に亡くなった方の自宅を調査し、手紙や契約書、請求用紙などで判明しますので、
相続放棄の熟慮期間が許す限り、地道に調べましょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
どんな財産を相続したのか全く分からない場合は、
大急ぎで借金を調査し、借金がない可能性が納得いくレベルまで高まったのなら、あとはゆっくりプラスの財産を調査しつつ手続きを進めていきましょう。
ただし、調査をしても見つけにくい債務というのは存在しますから相応の覚悟は必要です。どうしても怖い場合は期間内に相続放棄してしまうというのも一つの方法だと思います。
以上、お悩みの方の参考になれば幸いです。
関連ページ
遺言書の「清算型遺贈」に潜む罠—「譲渡所得税」について
近年、遺言作成の実務において「清算型遺贈(換価遺言)」を選択するケースが増えています。 「不動産を売却して現金化し、その代金を遺贈する」というこの手法は、公平な遺産分割や遺贈寄付(NPO法人などへの寄付)を実現するための有力な手段です。 しかし、私たち司法書士が実務上、最も警戒しなければならない「リスク」が一つあります。それが「譲渡所得税」の存在です。 1.「清算型遺贈」とは何か? 清算型遺贈とは、遺言の中で「不動産を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた残金を指定の人(または団体)に与える」という ...
ReadMore
新・中間省略登記とは? ~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 「中間省略登記」という名称は、不動産投資や転売に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。 私も最近、見聞きすることが増えましたので、この通称三ため契約について、知識を備忘録としてまとめました。 新・中間省略登記とは?~不動産取引の新たなスキームをわかりやすく解説~ 1.旧・中間省略登記とは? かつて行われていた「中間省略登記」は、不動産取引において、売主から買主に物件を渡す際、本来間に入る中間者(転売業者など)を登記上 ...
ReadMore
疎遠な相続人がいる場合、相続手続きはどう進めるべきか?
連絡が取れない相続人への対応方法と司法書士に相談するポイント 疎遠な相続人がいる場合の問題点 相続は、民法の決まりで、自動的に決定します。そのため、疎遠な相続人がいる場合、次のような問題が発生します。 遺産分割協議が進まない:疎遠な相続人が連絡を拒否したり、無視したりすることで、遺産分割協議が停滞してしまう。 相続放棄や遺産分割協議書に署名をしない:相続人が協議に参加しないと、手続きが進まなくなる可能性がある。 相続トラブルのリスク:相続人が不在のまま進めることで後々トラブルに発展することも ...
ReadMore
孤独死とは?もしもに備えて知っておくべき対応の流れと予防のための対策【司法書士監修】
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、孤独死とその対策についてと、司法書士が支援できることについて記載したものです。 孤独死とは?もしもに備えて知っておくべき対応の流れと予防のための対策 近年、「孤独死」という言葉を耳にする機会が増えました。高齢化社会の進行により、一人暮らしの高齢者や社会的なつながりを持たない人の数が増える中、孤独死のリスクもまた高まっています。 本記事では、万が一の際に備えて、孤独死が発生した場合の対応の流れ、法的な手続き ...
ReadMore
相続の基本を司法書士がやさしく解説|相続の流れ・登記・トラブル回避まで徹底網羅
相続の基本を司法書士がやさしく解説|相続の流れ・登記・トラブル回避まで徹底網羅 司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事では、相続の基本について、解説していきます。 はじめに|相続は「誰にでも起こる身近な問題」 「相続」と聞くと、どこか他人事のように感じる方も多いのではないでしょうか。 けれども実際は、人が亡くなると必ず発生する法的な問題であり、決して特別な家庭だけの話ではありません。相続手続きは時間制限があり、知らずに放置するとトラブ ...
ReadMore
名義変更ってどうやるの?相続の基本知識【司法書士がわかりやすく解説】
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です! この記事は、相続時の名義変更について解説した記事です。 名義変更ってどうやるの?相続の基本知識【司法書士がわかりやすく解説】 相続が発生したあと、よく聞かれるのが「名義変更ってどうすればいいの?」というご質問です。 不動産や預貯金、自動車、株式など、亡くなった方(被相続人)の財産を相続するには、名義を変更する手続きが必要です。 この記事では、名義変更の基本的な流れや注意点を、司法書士の視点からわかりやすく解説 ...
ReadMore
相続放棄、司法書士に依頼した場合の費用はいくら?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は相続放棄について解説した記事です。 徹底解説と失敗しない選び方 相続放棄とは?その重要性と専門家活用のメリット 相続は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産を受け継ぐ制度ですが、この「財産」には預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金、保証債務といったマイナスの財産(負債)も含まれます。 もし、負債がプラスの財産を大きく上回る場合、相続人はその負債まで引き継いでしまい、自身の ...
ReadMore
【知らないと損する】相続登記義務化をあらためて、ポイント解説
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されることになりました。 これにより、相続人は相続が発生した日から一定の期間内に登記を行わなければならなくなります。 この義務化の背景や、相続登記を怠った場合の罰則、そして今後の不動産相続における影響について、この記事では、細かい論点は割愛して、ポイントだけを解説します。 相続登記義務化の背景 不動産の相続登記が長期間行われないケースが多く、その結果として、土地や建物の所有者が不明のままと ...
ReadMore
横浜市瀬谷区・旭区・泉区の不動産名義変更ガイド:不動産取引をスムーズに進めるために知っておくべきこと
横浜市瀬谷区・旭区・泉区の不動産名義変更ガイド:不動産取引をスムーズに進めるために知っておくべきこと 横浜市瀬谷区、旭区、泉区にお住まいの方、またはこれらのエリアで不動産を売買・相続・贈与したいと考えている方々に向けて、 不動産の名義変更についてわかりやすく解説します。 不動産取引における名義変更は、法的に重要な手続きですが、意外と多くの人がその詳細を知らないことが多いです。 この記事では、名義変更のポイントを押さえておきましょう。 瀬谷区、旭区、泉区の不動産取引の特性 横浜市 ...
ReadMore
高齢者のひとり暮らし・生活お役立ち情報
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事は、お隣の大和市のパンフレットを読んでみて、わかりやすく、かつ、知らない制度もあったので、備忘録として記事にまとめたものです。 参考資料 生活お役立ちガイド これ一冊あればひとり暮らしもひと安心!第3版 生活お役立ちガイド 大和市 別サイトの記事 大和市が行う「おひとり様などの終活支援事業」が高齢者を幸せにしている理由 お悩み別 急病が心配。準備できることは? 高齢者見守りシ ...
ReadMore
不動産の共有状態の解消について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、様々な理由で、共有状態となっている不動産を、どのように解消するのかについて記載した記事です。 不動産の「共有」とは? 不動産を複数名で、所有している状態のことです。 ご夫婦で持分2分の1ずつ所有している場合は、「不動産を2名で共有している」と言いかえることができます。 不動産の共有の問題点 節税目的の場合や融資の受けやすさなどから、共有で不動産の取得を行う方も多くいらっしゃいますが、一般的に、共有状態はデメ ...
ReadMore
横浜市瀬谷区・旭区・泉区 相続登記・相続手続きでお困りの方へ
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です!相続登記は当事務所にお任せください 【瀬谷区・旭区・泉区にお住まいの方へ】 相続登記の手続きを放置していませんか?司法書士が丁寧にサポートします ◆「実家の名義、まだ父のまま…」それ、法律上は大きなリスクです 不動産の相続登記(名義変更)をせずに放置していると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。 ポイント 子供が家を売れない・リフォームできない 相続人が亡くなり、相続関係が複雑化する ...
ReadMore
相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...
ReadMore
令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...
ReadMore
公証証書の遺言書でも、専門家の事前チェックが必要な理由?
大切な想いを確実に未来へ。遺言書の専門家チェックが不可欠な理由 「自分で書いたからもう大丈夫」「公証役場で作成してもらったから安心」? そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ちょっと立ち止まって考えてみてください。 せっかくのあなたの想いを、より確実な形で未来へ繋ぐために、専門家の視点を取り入れてみませんか? 費用を抑えたい気持ちは山々だけど、専門家に頼む必要って本当にあるの? そのお気持ち、とてもよく理解できます。費 ...
ReadMore
令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。 基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。 ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...
ReadMore
仲介なしで不動産売買は可能なのか?リスクは?費用はどれくらいかかる?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 こちらの記事は、仲介なしで不動産売買をお考えの方向けの記事です。 不動産売買の新たな選択肢!司法書士が売買契約から登記まで完全サポート! こんな方におすすめの記事です 仲介手数料を節約したい方 不動産売買の手続きに不安がある方 安全かつスムーズに不動産売買をしたい方 信頼できる専門家に依頼したい方 見積もり・ご相談はこちらから 仲介なしでの不動産売買に需要がある理由 不動産の売買は、人生における大きな取引の一つです。 し ...
ReadMore
相続開始時の遺産の調査について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります 遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...
ReadMore
相続時の税金の落とし穴
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 専門外ではありますが、実務で個人的に「怖い」と感じた税金の落とし穴の話をまとめてみました。 この記事をご覧になって、ヒヤッとする方もいると思います。ぜひご覧ください。 相続時の怖い税金の落とし穴 実務で一番怖いのは税金です。誰にも相談せず、ネットや役所に聞きまわって自分で手続を進めた結果、数十万円損をしているケースを何度か見聞きしましたので、ご紹介します。 ◆必ず税理士に相談すべき場合 1.代償分割や、換価分割(不動産を売却して、相続人で分配する)を ...
ReadMore
特定財産承継遺言と遺贈による単独申請の適用時期
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 法律施行後の適用時期やその変更点について、毎回調べるのが大変なので、記事にしてまとめてみました。 特定財産承継遺言・遺贈について 旧制度と改正法の違いを分かりやすくまとめると、万能だった遺言書が、万能ではなくなり、その分、執行を行いやすくするために、遺言執行者の権限が拡大しました。 特定財産承継遺言 特定財産承継遺言とは、相続させる遺言につけられた名称であり、遺産分割方法の指定です。ここは基本知識なので、説明を省略します。 ...
ReadMore
相続・遺言のご相談
-

-
相続に関連する業務内容一覧
相続(不動産・預金・株式等) ↑↑ 戸籍謄本等の書類収集、遺産分割協議書などの書類作成、登記申請・預金解約などの相続手続き、財産調査や借金調査などをまとめてご相談になりたい方はこちら & ...
続きを見る
HOME