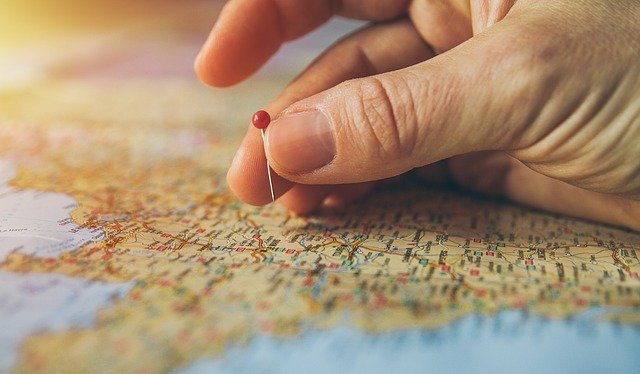司法書士 廣澤真太郎
当事務所では原則「公正証書による離婚協議書」の作成をお勧めしておりますが、公正証書の作成はお二人で公証役場に出席しなければならないので抵抗がある方や、手数料をできる限り抑えたいというご事情もあるかと思います。
私文書での離婚協議書の作成も行わないといった場合には、作成は義務ではありませんが、お子様の将来のためも、最低限「子供の養育に関する合意書」を作成しておく事をお勧めします。
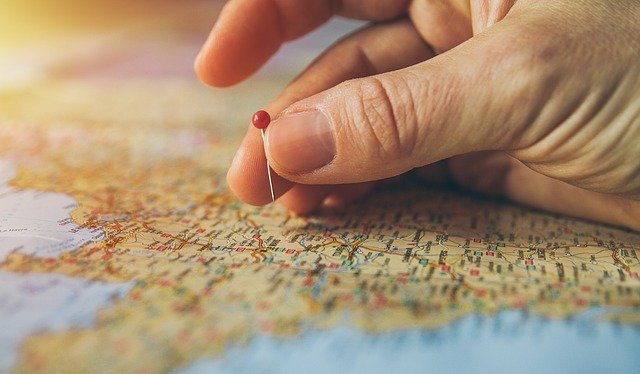
[toc]
子供の養育に関する合意書とは
百聞は一見に如かずですので、こちら御覧ください。また、こちらをダウンロードしてそのままご利用ください。
引用 法務省:子供の養育に関する合意書
このように、お子様の養育費と、面会交流(一方の親がいつどこで何時間お子様と会う事ができるか)について取り決めするための合意書です。
養育費とは
子供を教育したり、育てていくために必要な費用の事を言います。大原則は成人するまでですが、一般的に大学卒業までの医療費、教育費、生活費などがこれにあたります。
子の親には子供に自分と同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)があり、またその義務の程度は、たとえ親に余力がなくても負うべきとされています。
「最後に残された米一粒までも分かち合う義務」というように表現され、自分が食うに困っていても、子供を支えていかなければならないという厳しい義務があるわけです。
面会交流とは
子供と離れて暮らしている一方の父や母と会って話をしたり遊んだりと、交流することを言います。
子供は両親の離婚という出来事により「自分が悪かったのではないか。自分が嫌いになってしまったのか」といった気持ちになることがあり、「私たちはあなたの事が嫌いで離婚したんじゃないよ。」という気持ちを行動で伝えることのできる方法の一つになります。
そのため、お子様のより健やかな成長のためには大切な取り決めです。面会交流を通して、子供は両親に愛されているという実感を得ることで、心の底に自信をもって人生を歩むことができます。
Q&A
必ず離婚に伴い合意書を用意をする必要はあるのか?
ありませんが、お子様のための両親の取り決めですからできる限り書面に約束事を残し、2通作成して双方で保管して後々のトラブルを防ぎましょう。
お子様にとっては、両親が悪口を言い合ったり争っていること自体が最も精神衛生上よくないはずだからです。
当事務所では、継続的な支払いを要する養育費の取り決めがある場合、原則として「公正証書による離婚協議書」の作成を推奨しております。
合意書のみ残しておいた時に一方が養育費の支払いを怠った場合には、給与の差押えなどの前提として訴訟や支払督促などの裁判手続きを経る必要があります。
差押えは高度に専門的で複雑な手続きですし、弁護士への報酬も発生してしまい、費用面から断念する事にもなりかねません。
しかし、強制執行受諾文言が記載された公正証書を残しておけば、そのような手続きを経ることなくいきなり強制執行・財産開示手続を行うことができるので、お子様の安心とその固い両親の約束を将来にわたって担保することができるからです。
合意がすでにできている、または相手も協力的で話合いが容易なのであれば、公正証書による離婚協議書の作成をご検討ください。
養育費はどのような基準で決めればよいか?
裁判所の養育費・婚姻費用の算定基準表を参考にすると良いかと思います。
裁判所:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
計算例を挙げておきます。まずはPDFをご覧ください。
① 引用 裁判所 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
② 引用 裁判所:算定表の使い方
子供が両名とも14歳未満で、父母ともに会社員で、母が子供2名を引き取るケースで考えてみましょう。この場合、父が義務者で母が権利者となります。
【前提】
父の年収 400万円 (源泉徴収票の「支払金額」)
母の年収 200万円
【養育費の目安】
月額4~6万円
この金額を目安とし、協議離婚であれば現実的で可能な範囲で養育費を定めるのが妥当という事になります。
参考:法務省パンフレット
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...
ReadMore
令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...
ReadMore
令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。 基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。 ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...
ReadMore
一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...
ReadMore
外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。 1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...
ReadMore
株券の廃止手続き
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。 具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。 株券記載事項 (株券の記 ...
ReadMore
増資の登記について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。 増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。 増資の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...
ReadMore
役員変更登記(就任・退任)について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。 役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...
ReadMore
相続開始時の遺産の調査について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります 遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...
ReadMore
代表者(代表取締役等)の住所変更登記について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。 代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 司法書士にご依頼 ...
ReadMore
HOME