
この記事は、役所の無料相談会などでよくある質問をまとめたもので、ご依頼をご検討中の方向けの記事です。(執筆 令和4年)
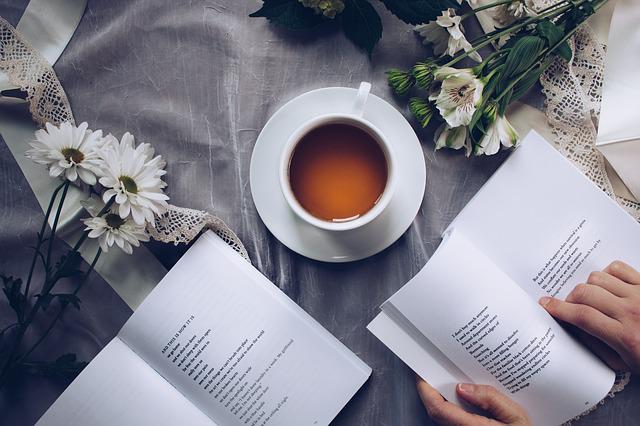
[toc]
相続登記でよくある10の質問
1.相続登記はしなければならないのでしょうか?
令和6年4月1日以降は、救済措置(相続人申告)が設けられるものの、登記申請は義務になります。よって、しなければならないかというご質問に対しては、いずれはしなければならなくなるとお答えしています。
また、この登記義務を怠った場合、10万円以下の過料が発生するものとされています。
また、私は義務化される前の現在においても、気づいたときに登記はしておくことを推奨しています。
なぜなら、登記をしない事による最大のデメリットでもありますが、放っておくと相続人が増えて権利関係が複雑化し続けていくことで、いざ登記しようとしたときに、相続人のうち一人でも未成年者・行方不明者・精神疾患をお持ちの方などがいると手続きが困難になるので、登記ができないという状況になることがあるからです。
一世代の相続ですら公正証書遺言を作成していおいた方がいい事案はありますから、鼠算式に増えてしまった相続人を調整して行う相続登記は困難になることが、容易に想像していただけると思います。
この場合、不動産の処分ができず、不動産を投資対象物として考えると、塩漬けのような状態になります。
よって将来的に、子孫のどなたかが本来発生しなかった費用や専門家報酬をすべて負担し、不動産の処分に挑戦なさることになるのかもしれませんが、経済的にも精神的にも負担になり、シンプルにもったいないとも思います。
2.司法書士に依頼せず自分でできないのしょうか?
正直に申し上げると、登記制度をご理解なさっていない方は、自ら登記をやってみるというのはお勧めできません。
登記は書類を集めて名前をただ変更すればよいという制度ではありません。権利がどのような原因で、いつ、誰にわたったのかをすべて整序判断したうえで、その内容を登記簿に反映させて公示する制度です。
つまり、その前提となる整序判断にミスがあると、長い年月が経過した後に失敗に気づき、取り返しがつかないという事もあります。
これは他士業の業務についても同様です。例えば、税金について理解されていない方が税務申告を行うのと同じで、申請した直後には発生した不利益に気づけませんよね。
数十万円の余計な納税義務が発生しているのだけれども、後日の請求にたいして「こういうものなのかなぁ。」と思ってしまうかもしれません。つまり、自分の致命的な失敗(損害)にさえ気づけない事もあるということです。
一般の方や一部の士業などが「登記は自分でできるよ」とお話しされているのを耳にしますが、その方々が責任をとってくれるわけではないので、保険の意味合いとしても、登記は司法書士にお任せいただくことを推奨します。
自分でやるのが難しいケース
とくに、次のようなケースではお近くの司法書士にご相談ください。
1.兄妹姉妹、甥姪が相続人の場合
この場合、収集する戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本の数が膨大になります。
約50通ほどになることもあります。収集するだけでも大変ですが、そこから相続関係を読み解くのも難しいので、この場合は専門家に戸籍収集からすべてご依頼になるのが良いでしょう。
2.相続財産に私道が含まれる場合
司法書士以外の士業もよく失敗しているのを見かけますが、被相続人の相続財産に私道が含まれている場合、この登記を漏らさないように物件調査を事前に行わなければなりません。
もし、相続登記をする際に漏れていた場合は、先述の登記を放置しているのと同様の状況になってしまいます。
3.法務局が遠方にある場合
すぐ近くに法務局があるのであればよいですが、申請書面や添付書類に誤りがあると大変です。
この申請書や添付書類の誤りの訂正は原則として、法務局窓口に行き登記官の指示に従って行う必要があるためです。
申請したあとで面倒に気付く事になってしまうので、このような場合はお近くの司法書士にご相談ください。
4.登記完了を急ぐケース
先ほどのご説明のとおり、登記は名前を変えるだけの手続きではないので、司法書士にご依頼いただいた場合でも全体で手続きに1~3か月の期間を要します。
ご自身で行う場合はもっと時間がかかりますので、余裕があるときに手続きすることをお勧めします。
5.亡くなった方の住民票が交付されないケース
相続登記に「権利書の添付は不要」とお考えの方がいまだに多いですが、このケースでは権利書、納税通知書、名寄帳など様々な添付書面が必要になります。
このようなケースは法務局と相談が必要になるので、司法書士にお任せいただくことをお勧めします。
3.相続登記に必要な書類を教えてください
当事務所にご依頼いただいた場合は、原則として次の書面で足ります。
この他の書類は、原則当事務所で代行取得しますので、ご準備いただく必要はございません。
① 相続人の皆様の印鑑証明書
② 相続人の皆様の本人確認書類のコピー
③ 場合により、権利書や固定資産税納税通知書の原本
4.相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
司法書士報酬はどこに頼んでもだいたい同じですが、税抜8~15万円に、実費が数万円、登録免許税が数万円から数十万円で、税込み総額で15~30万円の範囲内であることが一般的です。
まれに驚くほど低額で受任している事務所がありますが、信じられないミスをしているのを何度か見聞きしたので、安かろう悪かろうが当てはまるとお考え下さい。
5.登記が完了するまでの期間はどれくらいですか?
戸籍収集に1~2か月、書類のご案内に約1~2週間、登記申請から完了に約2~3週間なので、目安は合計約3か月です。
ただし、当事務所では球が来たら即座に投げ返す事をモットーとしておりますので、もう少し期間短縮できることが多いです。
6.遠方の不動産登記は依頼できますか?
例えば横浜市瀬谷区に在住の方が、広島県廿日市市の物件を持っている場合でも、当事務所にご依頼いただくことが可能です。
また、この場合ご自身で申請するのは困難ですので、お近くの司法書士にご相談ください。
7.相談の際の必要物はなんですか?
次の書類をご準備ください。
① 認印(三文判〇 シャチハタ×)
② 固定資産税納税通知書
③ 権利書一式 (登記済証、権利証、権利書、登記識別情報通知)
8.連絡先のわからない相続人がいますがどうすればいいですか?
司法書士にご依頼いただければ、司法書士が住民票を職務上請求で取得しますから、その住所宛にお手紙を送付してください。
9.被相続人の戸籍謄本が1通ありますが、これで足りますか?
通常足りません。被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までのものを揃えなければなりません。
具体的には、転籍前のもの、改製原戸籍、除籍謄本など5~10通が必要です。なお、これらは不動産登記にも銀行手続きにも利用し、1セット取得すれば足りますが、銀行の手続きに利用する場合には期限があるのでご注意ください。
10.相続した物件を売却する場合、取得者は誰にするのがいいですか?
ケースバイケースですので、こちらは面談時にご相談下さい。
まとめ

以上、相続登記に関するよくある質問にご回答しました。
登記申請は一生のうちにそう何度も経験することではなく、手続きをする前にはいろいろな不安を感じられると思います。
司法書士は相続登記、相続手続きなどの法律事務の専門家です。お問合せをいただければ、みなさまの不安に思われることについて、くわしいご説明をさせていただきます。
24時間お問合せフォームからご質問を承っておりますから、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから









