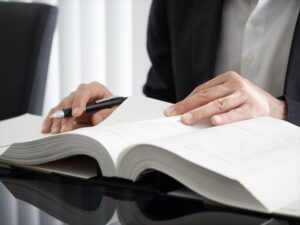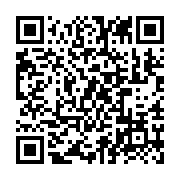不動産の名義変更(贈与・売買・離婚)のことでお悩みですか?
このような業務を”まるごと”相談できます
業務内容
✅ 不動産の調査、特定
✅ 注意すべき税金等のご案内
✅ 売買、贈与契約書、協議書などの作成
✅ 登記必要書類の収集、作成
✅ 登記申請、完了確認
✅ 権利書などをファイリングしてお渡し
✅ その他、確定申告や土地分筆の税理士・土地家屋調査士の紹介
こんなお悩みを、数多く解決しております
1.不動産を、親族に譲渡・売却したい
2.売却・贈与する際の失敗を防止したい
3.売却・贈与する際の税金について知りたい
4.離婚を考えているが、不動産はもらう予定(又は譲渡する予定)
5.離婚して数年経つが、ローン完済したので名義を変えたい
6.ローンが残っているが、不動産の譲渡をしたい
7.銀行から債務引受にあたって名義を変えるよう言われた
8.離婚までの段取りを知りたい
9.離婚協議書の公正証書作成をサポートしてほしい
ご相談事例
相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼
戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や見落としがちな注意点をアドバイスし、通常は半年以上かかる手続きをたった3か月で完了しました。
遺言書と記載のある封筒を複数部、発見し、何から進めて良いかわからないという状況からのご依頼
戸籍収集、家庭裁判所での遺言検認手続、その後の登記申請と預金解約、他の相続人の相続放棄手続きを代行し、かつ相続人への制度説明、進め方の提案、トラブルになりやすい注意点などを詳しくご説明、相続手続きで難しいところを全てお任せいただき、無事手続きを完了しました。
続きはこちらから
-

-
ご相談事例
ご相談事例 相続 相続の手続きについて、何から手を付けて良いかわからないという状況からのご依頼 戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請と預金解約を代行し、かつ相続人間で話し合うべき内容や ...
続きを見る

当事務所の特徴!
✅ ご依頼者様満足度90%以上 ※お客様アンケート・口コミ集計
✅ レスポンス、手続きスピードが驚くほど速い
✅ 士業事務所にも関わらず、こまめな連絡、丁寧な対応
✅ 司法書士が若く、柔軟に対応可能
✅ 案件により、ご自宅で事前見積りで気軽に相談
✅ 最短で相談日に登記書類送付&ご請求
✅ 全案件を司法書士が事務員任せにせず、直接対応
お客様の声
-

-
お客様の声
お客様の声アンケート ※アンケート調査の内容を一部抜粋しております。 司法書士 廣澤真太郎 少しずつですが、ご依頼をいただいた皆様にご協力いただいたアンケート調査の内容を、都度、更新して ...
続きを見る
外部サイトでの評価
比較ビズ:クチコミの一覧
Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所
オアシス司法書士事務所:お客様の声
一般的なご依頼の流れ

step
1お問い合わせ(ご質問・見積り)
step
2必要に応じて面談
step
3ご依頼
step
4必要書類のご案内
step
5お支払い
step
6登記申請、手続き
まずは見積り

まずは一度お問合せください!
お悩みがすぐに解決できるかもしれません
LINE らくらく相談

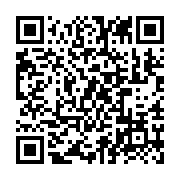
電話よりも気軽に質問が可能です!
メール相談フォーム 24時間受付中!
※執拗な電話営業が行われることはありませんので、ご安心ください。
↑↑
クリックで送信!
※返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けされる事がございます。「@oasis-lawoffice.com」のドメイン拒否をあらかじめ解除していただきますようお願い申し上げます。
無料メルマガの登録
メルマガ登録はこちら
暮らしに役立つ法律知識や、最新記事の情報をお知らせ!
司法書士に手続きをご依頼になった場合のメリット
✅ 誤った登記の理解による後日の後悔を防止できる
✅ 登記の際の税金でミスをしない
✅ 致命的な手続き上の失敗をしない
✅ 無難で安全に進めることができる
✅ 離婚時に話し合うべき内容や目安がわかる
✅ 離婚までの手続きの進め方がわかる
報酬・費用
報酬税込 5万5000円~ + 実費
案件により報酬費用は変動しますので、まずは事前見積りをご依頼ください。
お問合せフォームはこちら
新着記事一覧
離婚とその後のひとり親世帯について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 子どもの権利に関する研修を受けた際に、個人的に有益だと思った情報を令和3年度の情報を、国の調査結果から引用して記事にしてみました。 引用 厚生労働省:全国ひとり親世帯等調査結果報告 ひとり親世帯の現状 日本では、子どもの相対的貧困率は7人に1人であるところ、ひとり親世帯となると、ひとり親の2人に1人が貧困(その子も貧困)だそうで、詳しく知っておこうと思い、テーマとして取り上げてみました。 相対的貧困という概念はあいまいで ...
ReadMore
離婚した相手に養育費・扶養料は請求できるのか?請求方法や注意点【まとめ】
[toc] ※現在、養育費・面会交流のご相談は神奈川司法書士会でも30分無料相談を実施しています。 神奈川司法書士会特設ページはこちら 養育費とは何か? 未成熟な子どもが経済的、社会的に自立するまでの間に要する子どもの生活費の事です。 未成熟な子ども(大学卒業する頃まで)を育てている一方の親が、もう一方の親に対して監護養育費用の分担を請求することができます。 これとは別に、未成熟な子ども自ら、親に対して社会生活を維持するための費用を請求 ...
ReadMore
財産分与の流れについてわかりやすく解説
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 財産分与の基本がわかってきたら、次は実際に財産分与を行う流れについて知っておきましょう。この記事を見ると、離婚時の財産分与の全体像をイメージすることができます。 [toc] 離婚時には、5つのお金のことについて話し合っておく必要があります。 1.婚姻費用 2.慰謝料 3.財産分与 4.年金分割 5.養育費 このうち、財産分与の話し合い流れについてわかりやすく解説したいと思います。 ...
ReadMore
子供の養育に関する合意書(ダウンロード可)
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 当事務所では原則「公正証書による離婚協議書」の作成をお勧めしておりますが、公正証書の作成はお二人で公証役場に出席しなければならないので抵抗がある方や、手数料をできる限り抑えたいというご事情もあるかと思います。 私文書での離婚協議書の作成も行わないといった場合には、作成は義務ではありませんが、お子様の将来のためも、最低限「子供の養育に関する合意書」を作成しておく事をお勧めします。 [toc] 子供の養育に関する合意書とは 百 ...
ReadMore
当事務所の特徴

ご依頼になるとわかる
安心のスピード感!

関東圏に出張事前見積り
驚きのフットワーク!

お問合せフォームから
24時間受付可能!

明瞭で適切な
納得のコスト感!

効率的でらくらく
スムーズな手続き進行!

身近な専門家として
親切かつ誠実なご対応!
ご依頼の流れ

step
1まずはお問い合わせ

step
2見積り後、ご納得いただいてからのご依頼
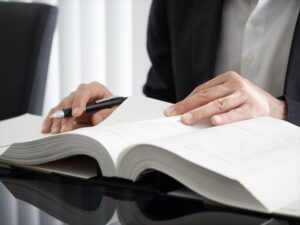
step
3書類収集、作成、署名押印等・費用のお振込み

step
4登記申請、各種手続き
※手続き内容により一部変更があります。
よくある質問
不動産の「財産分与」とは?
離婚に伴って不動産の所有権や共有持分を一方へ譲る事とした場合の手続きを財産分与と言います。
通常の贈与などと違い、夫婦で築いた共有財産を山分けするという考え方になるので、譲渡所得税を除いては、贈与税や不動産取得税などの税金が原則課税されないという特徴があります。
当事務所では、住宅ローンがある場合の財産分与はもちろん、所有権移転登記のみのケースなど離婚前や離婚後期間が経ってからのご相談でも、様々なケースの対応実績がございます。
財産分与による登記は離婚届提出後の手続きになりますから、相手方と連絡が取りづらくなったり、最悪手続きに協力してくれなくなることも想定されます。
そのため、中立な立場の司法書士に手続きをご依頼になることで、お二人の再出発をスムーズに行うことができるようになります。
離婚協議書(公正証書又は私文書の認証)の作成は、合意ができている場合には当事務所で公証役場とのやりとりや段取りをサポートすることも可能です。ただし、その内容についてご自身に「有利な交渉」を進める事についてのご相談は司法書士でなくお近くの弁護士にご相談ください。
報酬の相場はどれくらいですか?
財産分与による所有権移転登記は通常5万円~高額事務所で約20万円と、報酬に開きがあるのが特徴です。
場合により困難な案件もあるためです。当事務所では報酬5~10万円の範囲内に収まることが多いです。
税金はどれくらいかかりますか?
発生する主な税金は登録免許税です。 税率は、不動産の評価額×1000分の20です、
登録免許税はご請求時に一緒に税金もお預かりし、司法書士が法務局に対して代わりに納付します。
(計算例) 【不動産が土地建物】 土地1000万円 建物1000万円 もらい受ける持分2分の1 とする場合
2000万円 × 2分の1 × 1000分の20 = 20万円
【不動産がマンション】
建物1000万円
敷地①10億円
敷地②11億円
もらい受ける持分2分の1
敷地権割合100万分の2000 とする場合
建物 1000万円
敷地① 10億円 × 100万分の2000 = 200万円
敷地② 11億円 × 100万分の2000 = 220万円
(1000万円 + 200万円 + 220万円)× 持分2分の1 = 710万円
710万円 × 1000分の20 =14万2000円
離婚とその後のひとり親世帯について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 子どもの権利に関する研修を受けた際に、個人的に有益だと思った情報を令和3年度の情報を、国の調査結果から引用して記事にしてみました。 引用 厚生労働省:全国ひとり親世帯等調査結果報告 ひとり親世帯の現状 日本では、子どもの相対的貧困率は7人に1人であるところ、ひとり親世帯となると、ひとり親の2人に1人が貧困(その子も貧困)だそうで、詳しく知っておこうと思い、テーマとして取り上げてみました。 相対的貧困という概念はあいまいで ...
ReadMore
離婚した相手に養育費・扶養料は請求できるのか?請求方法や注意点【まとめ】
[toc] ※現在、養育費・面会交流のご相談は神奈川司法書士会でも30分無料相談を実施しています。 神奈川司法書士会特設ページはこちら 養育費とは何か? 未成熟な子どもが経済的、社会的に自立するまでの間に要する子どもの生活費の事です。 未成熟な子ども(大学卒業する頃まで)を育てている一方の親が、もう一方の親に対して監護養育費用の分担を請求することができます。 これとは別に、未成熟な子ども自ら、親に対して社会生活を維持するための費用を請求 ...
ReadMore
財産分与の流れについてわかりやすく解説
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 財産分与の基本がわかってきたら、次は実際に財産分与を行う流れについて知っておきましょう。この記事を見ると、離婚時の財産分与の全体像をイメージすることができます。 [toc] 離婚時には、5つのお金のことについて話し合っておく必要があります。 1.婚姻費用 2.慰謝料 3.財産分与 4.年金分割 5.養育費 このうち、財産分与の話し合い流れについてわかりやすく解説したいと思います。 ...
ReadMore
子供の養育に関する合意書(ダウンロード可)
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 当事務所では原則「公正証書による離婚協議書」の作成をお勧めしておりますが、公正証書の作成はお二人で公証役場に出席しなければならないので抵抗がある方や、手数料をできる限り抑えたいというご事情もあるかと思います。 私文書での離婚協議書の作成も行わないといった場合には、作成は義務ではありませんが、お子様の将来のためも、最低限「子供の養育に関する合意書」を作成しておく事をお勧めします。 [toc] 子供の養育に関する合意書とは 百 ...
ReadMore
離婚時の話し合いチェックリスト
[toc] 基本事項 基本事項 話し合いをして決まった内容 □ 婚姻費用(離婚までの間、婚姻中の相手に支払う生活費の事) 夫or妻が 〇年〇月〇日までに〇〇円支払うor毎月〇〇万円支払うor支払わない □ 慰謝料(どちらか一方にのみ離婚の責任がある場合に取り決めする賠償金) 夫or妻が 〇年〇月〇日までに〇〇円支払うor毎月〇〇万円支払うor支払わない □ 財産分与(婚姻してから2人の協力により形成したプラスの財産とマイナスの財産を清算して分け合う) ※重要 夫or妻が ・不動産 ・預金、有 ...
ReadMore
離婚後の手続きチェックリスト
[toc] 離婚後の手続きチェックリスト 氏名・住所・本籍地等の変更 公的証明書等 手続 場所 □ 住民票の異動届 ※転出届提出時に新氏名で変更するようお願いすると役所での手続きがスムーズです 市区町村役場 □ マイナバーカード、通知カード 市区町村役場 □ 印鑑登録 市区町村役場 □ 健康保険・年金 市区町村役場(会社員は勤務先) □ 運転免許証 警察署、運転免許センター □ パスポート パスポートセンター 公共サービス等 手続 場所 □ 水道 水道局 □ 電気 電力会社 □ ガス ガス会 ...
ReadMore
離婚とその相談先
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 離婚を行う場合には様々な手続きが必要になりますし、不安な点が多いのではないでしょうか。 離婚前後の相談先などを知っておくことで、後々の不安に備えておくことができます。 [toc] 地方自治体 地方自治体には市区町村に「男女共同参画推進センター」、女性専用であれば「女性センター」等の無料の相談所が開設されています。 カウンセラーや臨床心理士、弁護士などの相談員がDV、離婚、その他様々な家族生活の問題に対してとくに女性の抱える問題全般につい ...
ReadMore
離婚届とその見本
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 世間では離婚を後ろめたい事のように思う方が未だに多くいますが、離婚は通常、話合いを重ね、家族全員の未来を熟考したうえでの決断を経て成立するものであり、非常に前向きなものです。 このページでは離婚をする際の離婚届について解説していきます。 [toc] 離婚届の見本 離婚届は各市区町村役場で配布されているのでそちらをご取得ください。こちらがその記載例になります。 離婚届の記載例(妻が元の名前に戻る場合):法務省 ...
ReadMore
財産分与の基本
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 そもそも離婚時の財産分与とはなんなのかを知りたい方向けのページです。 [toc] 財産分与とは 「夫婦が築いた財産の清算のこと」をいい、離婚時に夫婦の一方から財産の分与を相手方に求めることができます。 婚姻期間中に築いた夫婦の財産は、お互いが助けあったからこそ築けたものだから、離婚時にはそれぞれ公平に分け合いましょうと請求できるわけですね。 請求できるとは… 請求できる、すなわち求めることができるとはどのよう ...
ReadMore
財産分与に関わる税金の一例
司法書士が節税や税金対策のアドバイスを行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
登録免許税
移転する不動産の評価額の合計額に20/1000の税率を掛けて計算します。司法書士が預り金から法務局に対して代わりに納付します。
印紙税
財産分与契約書に不動産の金額記載がある場合には、その金額に応じて印紙を貼付する必要があります。ない場合には200円の印紙を貼付します。
みなし譲渡所得税
税金の専門家ではないので理解しにくくちょっと納得いきませんが譲渡した方には税金が発生します。
譲渡所得税とは簡単にいうと不動産を取得、譲渡した時に生まれたキャピタルゲイン(差益)について課税される税金なのですが、譲渡が無料でも関係なく言葉どおり譲渡所得があったとみなされて税金が発生するようです。
ただし、居住していた不動産の贈与であれば居住用財産の控除が使えますから、きちんと確定申告さえ行えば多くのケースで実質負担はないことが多いでしょう。
贈与税や不動産取得税
財産分与は正確には贈与や取得ではなく、もともと夫婦で築いて持ちあっていたものを分離して分け合うだけというものなので、課税されないのが通常なようです。
ただし、不当に多額の財産移転を行ったりすると課税される場合もあるようなので注意が必要です。詳しく知りたい方はお近くの税務署にご相談ください。

まずは一度メール又はお電話ください。
ご依頼前に事前相談・見積もりを致します。
※相見積もりをご検討の場合は事前にお知らせください。
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから
相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...
ReadMore
令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...
ReadMore
令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。 基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。 ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...
ReadMore
一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...
ReadMore
外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。 1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...
ReadMore
株券の廃止手続き
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。 具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。 株券記載事項 (株券の記 ...
ReadMore
増資の登記について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。 増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。 増資の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...
ReadMore
役員変更登記(就任・退任)について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。 役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...
ReadMore
相続開始時の遺産の調査について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります 遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...
ReadMore
代表者(代表取締役等)の住所変更登記について
司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。 代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 司法書士にご依頼 ...
ReadMore
HOME