
この記事では、民法改正のうち、債権法に関する部分で忘れやすいところを、備忘録としてまとめています。ご自由にご覧下さい。
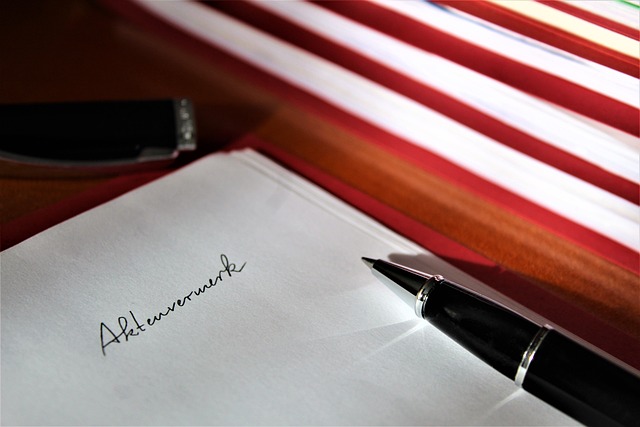
[toc]
意思能力制度の明文化
意思能力を有しない者がした法律行為は無効。これまで、判例や学説の中で、異論なく認められていたが、明文の規定がないため、創設。
原状回復義務は、現に利益を受けている限度にとどまる。
錯誤についての改正
錯誤の効果が無効でなく取消となった。また、判例に基づく要件を明文化した。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
錯誤取り消しには、その事情がないと意思表示しなかったであろう事情や、普通の人でも、錯誤がないと意思表示しなかっただろうと客観的に認められることが必要。
代理人の行為能力
任意の代理人であれば、代理人を選んだのは本人なのだから効果を本人に帰属させるべきだが、制限行為能力者が法定代理人はそのような場合に該当しないため、あらたに但し書きを創設。
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
解除の効力
履行不能による解除について、帰責事由がない場合でも、一般に解除を可能とした。ただし、債権者に帰責事由があり、履行不能となった場合は除く。
細かい解除の要件については、明文化して条文から読み取れるようにした。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
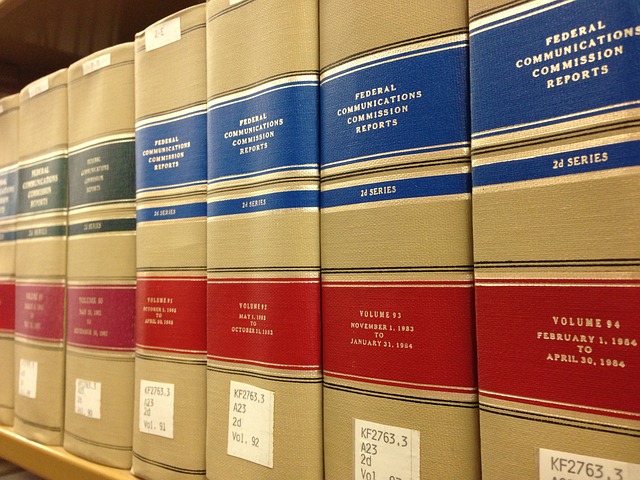
瑕疵担保責任
「隠れた瑕疵がある」という要件を、目的物の種類、品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改めた。 瑕疵担保責任→契約不適合責任
よって、契約書作成時には、契約の目的が重要視されることとなった。また、買主の請求できる権利をわかりやすくした。
買主の権利を明文化
①追完請求権
②代金減額請求権
③損害賠償請求及び解除権
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
債権者代位・詐害行為取消権
判例で作られてきたルールを明文化し、わかりやすくした。
債権者代位権について明文化されたもの
① 金銭債権等は直接、債権者への支払いを求めることができる。
② 債権者の権利行使後も被代位権利についての債務者の処分は妨げられない。
③ 債権者が訴えをもって代位行使をするときは、債務者に訴訟告知をしなければならない。
詐害行為取消権について明文化されたもの
① 債権者は、債務者がした行為の取消しとともに逸出財産の返還(返還が困難であるときは価額の償還)を請求することができる。
② 詐害行為取消しの訴えにおいては、受益者を被告とし、債務者には訴訟告知をすることを要する。
③ 詐害行為取消権の要件(詐害行為性、詐害意思等)についても、類似する制度(破産法の否認権等)との整合性をとりつつ、具体的に明確化する。
連帯債務
連帯債務に関して見直しを行い、絶対的効力事由を減らした。
| 行為 | 効果 |
| 連帯債権者による履行の請求 | 可分債権の場合、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 |
| 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因 | 他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 |
| 連帯債務者の一人と債権者との間に更改 | 債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。 |
| 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用 | 債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。(相殺援用しない場合、履行を拒める) |
| 連帯債務者の一人と債権者との間に混同 | その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。 |
| その他の行為 | 連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。 |
弁済について
債権者が、債務者の意思をしらなければ、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者らの弁済についても、有効とした。
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
危険負担
債務者主義を採用。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
消費貸借
要物契約だったが、合意でも可能に。
融資の前に借主が契約を解除し、損害が発生した場合、限定的な場面でのみ請求も可能。
(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
(準消費貸借)
第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
賃貸借
敷金・原状回復義務
トラブルが多かった、敷金や原状回復義務について明文化。
礼金、権利金、保証金とあっても、未払い債務の担保目的であれば、それらは全て敷金ということに。
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
通常損耗、経年劣化に当たるもの
・家具の設置によるへこみ、設置跡
・テレビや冷蔵庫による壁の黒ずみ
・地震で割れたガラス
・鍵の取り換え ※紛失、破損を除く
通常損耗、経年劣化に当たらないもの
・引っ越しの際のひっかき傷
・タバコのヤニ、臭い
・飼育ペットによる臭い、傷
・用法違反による設備の破損等
国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
オーナーチェンジ
賃料を賃借人に対して請求するには、所有権移転登記が必要。
存続期間
最長50年に延長
請負
完成した仕事の結果に応じて支払われるものとされていたが、中途解約のケースでも、報酬が請求可能である場合を明文化。
また、請負人は、売主同様の契約不適合責任を負う。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
知識ページ一覧
知識ページをご覧になりたい方はこちらから









